農業の未来コウジョウ研究所のメンバーで、淡路島に。吉備国際大学を訪問したあとは、フレッシュグループ淡路島の代表 森さんにお話をうかがいました。
フレッシュグループさんって、こんなグループ
それぞれが農園を営みながら、「個々ではできないことをグループで助け合いながら課題を解決していく」ことを目的に集まってできたフレッシュグループ淡路島。島外から移住してきた新規生産者や地元農家、年齢も経歴も多岐にわたるメンバーが一緒に活動しています。「多くの人に農業に興味を持ってほしい」という想いのもと、農産物を全国のお客様に提供するだけでなく、農業体験の受け入れや農園内で採れたての野菜の販売もおこなっています。
また、淡路島の北部には、栽培効率の悪い中山間地の田畑が拡がり、耕作放棄地も増えています。そのような農地や農村の保存活動を通して農業を持続可能な状態にしていくことを目指しながら、若い人に農業に興味を持ってもらい、魅力あるものにしていく活動を続けています。
こんにちは。私たち「農業の未来コウジョウ研究所」は、兵庫県の揖保郡太子町という場所で、プラントを開発して野菜を栽培しています。今日はフレッシュグループさんの色とりどりな野菜についてや、お客さまからの要望にお応えする出荷の仕組みなどをお聞きできたらうれしいです。そして、ぜひ森さんの視点でプラントでの水耕栽培についてもアドバイスを頂けたらと思います。
こんにちは。フレッシュグループ淡路島、代表の森です。
今、こちらでは何をしているのですが?

今、まさに出荷の最中です。昨日までに入ってきたご注文分を朝から収穫して、昼までに集まってきた農作物を、夕方までに出荷するのが毎日のサイクル。この場所がいっぱいになる量の野菜を、全国にお届けしています。カラースティックニンジン、イタリアンパセリ、バジル、ルッコラ、ハーブいろいろ、パプリカ、たまねぎ、キャベツ、エディブルフラワーなど品目は様々です。

こんなにたくさんの種類をどのようにつくっているのですか?
農家ごとに、3~5種類を栽培しています。それらが集まってきて、20~30種類になっているんです。1つの農家で多品目をつくると、1品目あたりの収穫量が少なくなり、出荷量が限定されてしまうことで、流通にのらなくなってしまいます。そういった課題があるので、この仕組みにしています。また、勤務体系についてもグループの役割分担・必要な人数のコントロールを徹底し、生産性をあげられるように工夫をしています。
なるほど!そうした仕組みで20~30種類の出荷を実現しているのですね。ところで、ニンジンを年間通じて育てているって珍しくないですか?
そうなんです。うちの一番人気がカラースティックニンジンで、3色(パープル、イエロー、オレンジ)あります。これらは2週間に1度のペースで種をまいていて、年間30作おこなっています。通常7・8月に種をまいて12月に収穫することが多いのですが、年間30作をやっているのは自分たちだけだと思います。
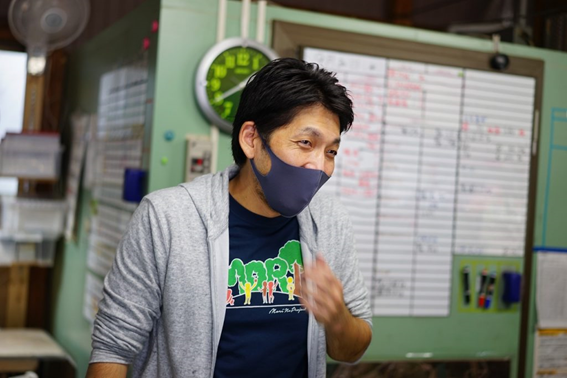
このカラースティックニンジンは、お客さまがメインのお料理に合わせて色が選べることがポイント。様々な色の展開をお料理の中で実現できると重宝してもらっています。このようなフックになる人気商品があることで、お客さまとの出会いのきっかけも増え、他の品目もふくめた年間を通じた継続的なご購入につながっていると考えています。あと、「規格の柔軟性」についてもお客さまから喜んでいただいています。
「規格の柔軟性」って、具体的にはどういったことなんですか?
業務用・小売り用のパックサイズや料理人などお客さまの要望にあわせて使いやすいサイズで、品質の一定した野菜の提供を実現しています。手間はすごくかかりますが、細かく仕分けの段階をわけていて、例えばスティックニンジンでは6段階にもなります。また、梱包コストなどをおさえて、購入しやすい価格設定を心掛けています。年間を通した品種の豊かさだけでなく、こうした「規格の柔軟さ」や、「購入し続けやすい価格」も飲食店や小売店さんに長期的にご注文をいただけるポイントかと思います。

私たちのプラントでも「味」や「食感」、「保存期間」などで、他の野菜と差別化ができるように品質をさらに高めていきたいです。フレッシュグループさんのお客さまからうれしいお声はありますか?

うちはすべて手選別なので、「ルッコラセルバチコ」など選別精度が高いことが特徴です。カマで収穫すると、味がぼやけた葉っぱが混ざりがちですが、そうした葉っぱは外して、味の強いところだけを出荷していて、「味が濃いと」とお客さまから高く評価いただいています。
そして、もう1点、「フレッシュハーブ」の栽培期間が通常とちがうことも特徴です。1か月~2か月程度で植えて収穫しきる短サイクル栽培ではなく、半年ぐらいのサイクルで栽培しているため、株の成長が進み、味が濃く食べごたえのあるものに育ちます。ただ、「生で食べる場合は、うちの野菜は味が強すぎることもあるので、料理によって選んだほうがよい」ともお伝えしています。

なるほど。選別精度や栽培期間のサイクルが味の濃さに影響するのですね。
これまで苦労したことはどんなことですか?
天候不順や天災により、一気に農作物が出荷できなくなってしまったときは大変でした。数年分の利益をもっていかれるので、重なるとかなり厳しいです。露地栽培のつらさですね。
そしてルッコラセルバチコなど、特殊な種類の栽培となるとマニュアルがないので、スタート時はとても苦労しました。細いスティックニンジンについてもマニュアルがありませんでした。ニンジンの色によって生育の波がちがう。伸び方もちがう。こういった特性に合わせて、種をまく量とタイミングを考えないといけないといったことを少しずつ学んでいきました。
では少し農園を歩きましょうか。

こちらのラディッシュとからし菜は、種をまく時期をずらして、日々の需要に対応できるように計算しています。
そして、ここ淡路島北部の中山間地には小さい農地が多いので、定期的に畑と品種を回転させて、栽培効率をあげていかなくてはなりません。
畑を見ると、とても計画的に、丁寧に、栽培・収穫をされているのがわかりますね。わたしたちも、より料理人さんや消費者のみなさまに向けて価値を提供できる作物を追求していきたいのですが、プラントでの水耕栽培におすすめのものはありますか?
プラント栽培は、そんなに大きく建物を増やせないですよね。狭い土地を活かして農業をするには、付加価値をつけることが大切だと思います。小面積で価値のあるものを追求し、いかに収益あげるかを考えると、エディブルフラワーは、単価もよいし、種類が増えてくれば面白いのではないでしょうか。一般的な品種としてはビオラが多いですが、葉っぱの重さが軽いので、むずかしい。私たちも食べられるカーネーションの栽培にチャレンジ中です。もしいろいろなお花の栽培が実現すれば、食も豊かになると思います。

食べられるカーネーション!?楽しみですね。
それにしても、ほんとに気持ちの良い畑ですね。フレッシュグループさんは多くの人に農業に興味を持ってほしいという想いから、農作物の出荷だけでなく、農業体験の受け入れや農園内で採れたての野菜の販売もおこなっておられると思うのですが、これからの農業の未来についてどう考えておられますか?

農家が役割分担をしていくことが大切だと考えています。
例えば、1農家で20、30種を栽培し、少量で出荷しているスタイルもあります。こういった少量多品目の農家はすごくめずらしいものをつくることができるし、めずらしい野菜を求める飲食店さんの需要に応えることができます。一方、僕らみたいに全国の大手のお客さんともやり取りをし、バジル・イタリアンパセリ・ルッコラセルバチコのようなちょっと特殊なものをある程度の量の規模で出荷することのできるスタイルもある。事業規模・形態などによって役割分担をすることで、未来の農業を持続可能にしていけるのではないかと思います。

細かく規格を分けて提供するなど、既存の農家がやりたがらないところを自分たちはやっていこうと決めました。農業のどこに課題があるかを考えることで新しいことが始められると思っています。
課題を苦労をいとわずに解決していきながら、未来の農業を切り開いていく森さんから、たくさん勉強をさせていただきました。今日は貴重なお話を聞かせていただいて、ありがとうございました!








